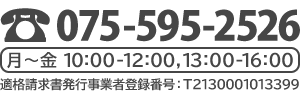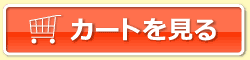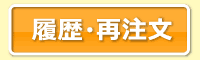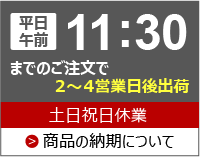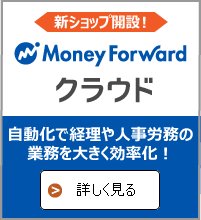勤怠管理のすすめ。
給料王と連動するツールまとめ!
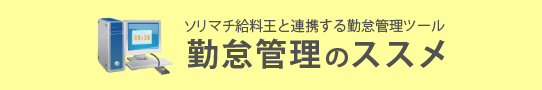
ソリマチユーザーの皆様、御社の勤怠管理はどのようにされていますか?
- タイムカード?
- 紙の出勤簿?
- エクセル?
- 給料王へ直接手入力?
会社として新たにタイムカードを導入しよう、検討してみようとお考えの企業様に、最新の勤怠管理手段にはさまざまな選択肢があることを示すとともに、いくつかの製品を紹介してまいります。
もちろん、すでにタイムカードをご利用中であっても、役立つ情報が盛りだくさん。ぜひご覧ください。
◇目次◇
1.なぜいま勤怠管理か?
2.勤怠管理の方法
タイムカード
データ連携型タイムカード
勤怠管理システム
3.驚くほど安くなった!勤怠管理システムの数々
4.ミモザの「小規模企業におすすめの製品」
選び方のコツ
ICタイムリコーダー
単機能タイムレコーダー
5.勤怠管理システム導入の注意点
自社の就業体系に沿った運用ができるか?
切り替え時期
使用方法の周知、練習
システムに合わせて、運用を変えてく部分も必要
なぜいま勤怠管理か?
昨今、勤怠管理システムの見直し、置き換えが盛んとなっています。
長時間労働を抑えようとする機運が高まったり、従業員のこころの健康状態を調べるストレスチェック制度が導入開始されたりなど、労働者の衛生環境の向上が声高に求められていることが背景にあります。
また、インターネットにより労働法や判例などの知識が普及し、労働者の権利意識の向上とともに労働紛争や過去の残業代請求訴訟が多発していることなども、無縁ではないでしょう。
「勤怠管理」という仕組みが、単に労働者の出退勤時間を管理するものから、社員と会社、お互いを守るものへと、役割を発展させつつあります。
ご存じのとおり、タイムカード自体は、労働基準監督署に設置することが推奨されていつつも、義務化されてるものではありません。
だからと言って、これを設置しないことは、会社として社員の客観的な勤務記録を何も保持できていない状況に他なりません。
これは、会社の大小に係る問題ではありません。
今は、タイムカードも電子化された便利な製品が多数出ています。
これを機に、今一度自社の勤怠管理の仕組みを、整備・見直してみませんか。
勤怠管理の方法
勤怠管理とは、社員の出退勤、休憩や残業、欠勤などの状況を客観的な記録として蓄積・管理し、給与計算の根拠とするための一連の仕組み・業務です。
目的はすべての会社で共通しますが、方法については千差万別です。.
一般的にはタイムカードを利用

一番多くの会社で取り入れられているのはタイムカードでしょうか。
縦長のカード式の用紙を、タイムレコーダーと言われる機器に通すと、日付と時刻が印字されるものです。
いまでは大規模な事業所を中心に電子化が進んでいます。
一般的には、値段が高くなればなるほど、機能が増えていきます。
具体的には、6桁対応(外出・休憩の記録が可能に)になったり、早番・遅番などのシフトを登録できたりする機種もあります。
(長所)
機器が安価
慣れ親しんだ方法で、誰もが抵抗なく使える
すぐ使い始められる
(短所)
入力・集計作業が大変(手入力の量力やミスの恐れ)
タイムカードなど、紙の資料が増えてしまう
消耗品コストがかかり続ける(カード、インクリボン)
データ連携型タイムカード

タイムカードを使う方法はそのままに、勤怠記録を自動でデータ化・集計してくれる機能をつけた「賢いタイムレコーダー」です。
データは、毎月締日に本体とパソコンをケーブルでつないで取り出します。
データの閲覧には専用のソフトを使います。
こちらも値段とともに機能が増します。
代表的な製品名
- TimeP@CK(タイムパック)
- タイムロボ など
(長所)
入力・集計作業が改善される(自動化による高精度化)
慣れ親しんだ方法で、誰もが抵抗なく使える
すぐ使い始められる
大手メーカー製なので安心感あり
(短所)
機器が高価なため、初期コストが嵩む
消耗品コストがかかり続ける(カード、インクリボン)
勤怠管理システム

打刻にパソコンシステムを利用し、タイムカードを使わない方式です。
打刻の方式としては、
- 社員証などのICカード
- 会社支給の自席パソコン
- 会社支給のスマホやタブレット
を利用することが多いですが、個人の端末から打刻できるるものも。
データは人事担当者のパソコンや、システム事業者のデータセンターなどに蓄積します。
一口に「勤怠管理システム」と呼んでいますが、その種類は多く、選定するのは大変です。数千人規模の大企業向け製品から、数人から使えるものまで、費用面でもピンからキリまであります。
予算や自社の人員規模、譲れない機能などを軸に比較検討します。
(長所)
入力・集計作業が発生しない(ペーパーレス)
入力状況、途中経過をリアルタイムで閲覧することができる
消耗品不要なため、ランニングコストが抑えられる
自社に合った複雑な勤務体系・就業規則などに適合させやすい
初期コストが低いものが多い(無料のものも)
(短所)
サービスがあまりにも乱立し、何を選べばいいかわかりにくい
サービス選定のための比較検討が大変
知らないメーカーの製品を使うことへの不安
初期設定のために、担当者にもある程度の技術と手間が必要
代表的な三種を見てきました。 他にも、全従業員に同一フォーマットの出勤簿をつけさせたり、外勤営業職の方などにみなし残業制を採用したり、上記には当てはまらない様々なケースがあります。
驚くほど安くなった!勤怠管理システムの数々
ここでは、「勤怠管理システム」について、少々深く見てみましょう。
先ほどの項で、勤怠管理システムについては、なんだか掴みどころのない話になってしまいました。
それは、あまりにも多くの種類のシステムが乱立しているからですが、小規模な企業で使うとなれば、ある程度俎上に乗るものは絞られてきます。
比較してみよう!
|
製品・サービス名 |
ICタイムリコーダー | TOUCH ON TIME | KING OF TIME | CLOUZA |
|
運営元 |
株式会社オープントーン |
株式会社デジジャパン |
株式会社ヒューマンテクノロジーズ |
アマノビジネスソリューションズ株式会社 |
|
管理可能人数 |
1名~ |
1名~ |
1名~ |
1~500名 |
|
料金 |
220円~/人 |
330円/人 |
330円/人 |
無料~220円/人 |
|
備考 |
PC、スマホ、ICカード打刻対応 |
PC、スマホ、ICカード打刻対応 |
PC、スマホ、ICカード打刻対応 |
PC、スマホ、ICカード打刻対応 |
|
給料王との連携 |
○ |
○ |
○ |
△(有償版のみ) |
※表示価格は全て『税込価格』です。
料金をご覧になっていかがでしょうか。
紙のカードを集めて入力・集計する作業にかかる労力は、慣れた担当者であっても、対象人数が多ければはかり知れません。ましてや、毎月のことですから、1年、2年のスパンで見ていくと、貴重な時間を多く割くことになります。
これを機械(システム)に任せられれば、他の仕事に時間を振り向けることができます。機械は入力ミスをしませんし、計算も間違えません。
こう考えると、安くも感じられるのではないでしょうか。
実際、同種のシステムの価格下落も進みました。これは、同様のサービスが近年急激に普及したことによる競争の側面が強いです。
ミモザの「小規模企業におすすめの製品」
ここからは弊社の意見です。
システム選びのコツ
安いほうがいいですよね。
私もそう思います。
でも安すぎるのも怖いですよね。
安い部類に入っていて、かつ安心できるもの。
安心とは?
アフターサービスや、困ったときのサポートが充実しているもの。
突然のサービス終了に見舞われないよう、運営主体が安定しているもの。
ICタイムリコーダー
当社がおすすめしているのは、勤怠管理システムの「ICタイムリコーダー」です。
(おすすめポイント)
・必要最低限の機能を網羅している
かつ、あまり余計な機能がない(無駄がない)
・初期設定にしっかり付き合ってくれる
同じ画面を見て電話でマンツーマンで対応してくれるのは心強い
・ある程度の拡張性がある
・やっぱり安いのは大切
詳しくはICタイムリコーダーのページでご紹介します。
タッチオンタイム
従業員数が100を超えて(超える見通しであり)
生体認証機器などの利用が必要になるのであればおすすめしたい製品です。
・ICタイムリコーダーのメリットはすべて内包
・その代わり少々お高い。月額330円(税込)/ID
データ連動型タイムレコーダー(タイムパック)
今さら手集計の単機能タイムレコーダーをおすすめするわけにはいきません。
データ連動型、いわゆる自動集計のタイムレコーダー導入は業務生産性を高めるうえで譲れないポイントです。
社員数の多寡にかかわらず、非常に便利です。
(おすすめポイント)
誰もが使い方を知っているタイムカード方式。とっつきやすさはこれにかなわない。
だからこそ、高価です。
・アマノ社のTimeP@CK(タイムパック)シリーズが、給料王へのデータ連携に対応しています。
勤怠管理システム導入の注意点
それでは、最後に勤怠システムを導入にする際、注意すべきことを列挙していきます。
自社の就業体系に沿った運用ができるか?
こう書くと一言ですが、これを確認するのはなかなか大変です。
ネックになるのは、それぞれの会社ごとの独自ルールや「運用上のクセ」です。
長い休憩が入ったり、日付をまたいだり、といったことに一つずつ対応できなければなりません。
タイムレコーダーですと実機テストは難しいです(メーカー主催のデモや展示会に出かける必要があります)が、勤怠管理システムは、各社、無料体験を用意しています。
カードリーダーなど、打刻用機器の貸し出しもあります。
およそ一か月間、実際のサービス画面などを利用し、テストを行うことができます。
一度に何社も頼まなくていい
うっかり見積もり比較サイトなどで申し込んでしまうと、営業の電話が鳴りっぱなし…なんてことに。
一度に多数を比較することはできませんから、アタリをつけたらまずは一つ、実際のデータを登録して徹底的に使ってみることをおすすめします。
すべての機能を使わなくていい
付いているから、もったいないからと言って、無理にすべての機能を使う必要はありません。
シフト管理など、使い慣れた書類やファイルデータがあれば、そのほうが生産性は高いかもしれません。今ある仕組みでいいものは、今のままでいいのです。
逆に、いかに機能が多くついていても、使わなければ宝の持ち腐れです。
まずは打刻のみ導入してみて、徐々に利用する機能を増やしていくのも一つの方法です。
切り替え時期
システムの切り替えを行うタイミングは、もちろん給与締日に合わせることがおすすめです。
さらに、年末年始など現場が忙しい時期は避け、月曜、金曜など会社ごとの繁忙曜日に重ならないように配慮したいものです。
切り替えは一気に進めるのが肝要ですが、事前に本社管理系など一部の部門・グループのみテスト導入をして、利用時に寄せられる問い合わせやトラブルなどをある程度想定しておくとスムーズです。
使用方法の周知、練習
特に複数拠点で利用する必要性がある場合には、部門・グループごとに指導役をつけ、その方にある程度の想定問答などを伝授しておくと、混乱を抑えられます。
疑問点を吸い上げて全体に公表する姿勢も持ちたいですね。
システムに合わせて、運用を変えてく部分も必要
何か新しい仕組みを導入すれば、不平や文句は必ず出るものです。
全員の好みを聞いていればキリがありませんから、誠実に対応しつつも、適宜受け流す姿勢も求められるのかもしれません。
そして気を付けたいのは、勤怠管理を行う場合の、時間の解釈や見解の統一です。
そもそもタイムカードは出退勤時間を記録するものであり、打刻時間イコール労働時間という性質のものではありません。しかし、この解釈は社員側と経営側とで往々にして食い違うものです。
業務時間の「端」の扱いや、そもそも社員の出退勤のタイミングは、始終業時刻に対して常識的な範囲に収まっているのかなど、この点を今一度点検し、「あるべき姿」を労使双方で確認するとともに、場合によっては社会保険労務士などの手を借りながら、しっかりと明文化しておきましょう。
タイムカード・勤怠管理システムは、「人」と「会社」そして「社長」を守る大切な仕組みです。
残業代をめぐる高額な支払い命令が出る例は後を絶たなくなっています。
同様の紛争は今後増えることはあっても減りはしないでしょう。憂いでも嘆いても、もう戻ることはありません。
それ以前に、会社には従業員が健康で安定して勤務し続けられる環境を整える「安全配慮義務」があります。システムなど仕組みの導入により過度の残業が継続していないかなどを可視化し、十分注意しましょう。
これを機に、ぜひあなたの会社の勤怠管理の仕組みも、再点検なさってくださいね。